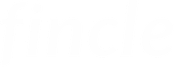3dman_eu / Pixabay

日本は少子高齢化が進み、もらえる年金がだんだん少なくなり、もらえる年齢も徐々に上がりつつあります。
私たちが年金を貰う頃には、もっと受給額が減っているかもしれません。あるいは、現在の仕組みとは大幅に異なっているかもしれません。

そこで2001年より始まったのが、自分の老後のために積み立てる年金制度、確定拠出年金制度です。
この制度は公的年金など他の制度と比べ新しく、認知度が低いのが現状です。「確定拠出年金制度っていったい何?」という人も少なくないと思います。
確定拠出年金には、企業が運営主体となる「企業型」と、国民年金基金連合会が運営する「個人型」の2種類があります。
今回は個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ/individual-type Defined Contribution pension plan)について解説していきます。
目次
個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)とは?

3dman_eu / Pixabay
上記でもお話したように「公的年金だけでは老後が不安」という方がほとんどでしょう。
しかし老後のための資金を貯蓄するだけでは金利がほとんどつかず、全然効率的ではありません。そこで注目されているのが個人型確定拠出年金なのです。
個人型確定拠出年金を簡単に説明すると、節税しながら老後のお金を積み立てる制度です。個人型確定拠出年金の節税効果は絶大で、『積立』、『運用』、『受取』時に節税が可能です。
| 積立時 | 掛け金の分は所得税と住民税から控除される。 |
| 運用時 | 運用で得た利益は非課税になる。 |
| 受取時 | 退職所得控除や公的年金等控除の対象となる一定額が非課税になる。 |
表からも分かる通り、実はこの制度をうまく利用すれば、年収500万円の人だと10年間で60万円近く節税することができます。なんと銀行で定期預金したときの利回りに換算すると、20%以上に上ることもあります。

そうなのです!節税の仕組みについては個人型確定拠出年金のメリットのところで説明しますね!
個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)のメリット

3dman_eu / Pixabay
ここでは個人型確定拠出年金のメリットについて見ていきたいと思います!
メリットをざっと挙げると下記になります。
- 所得税と住民税の控除が受けられる
- 運用で得た利益は非課税になる
- 受取るときも非課税か控除を受けられる
- 運用する金融商品を何度でも変更可能
- 本人が死んでも遺族が受け取れる
- 自己破産しても受給資格は残る
- 積立すれば無駄遣いが減る
たくさんのメリットがありますね!早速1つずつ詳しく確認していきましょう!
所得税と住民税の控除が受けられる
この記事の冒頭部でも紹介しましたが、個人型確定拠出年金の最も大きなメリットが、その掛金を本来支払うべき所得税と住民税から控除してもらえるということです。
しかしいったいどれくらいの節税効果があるのか、年収500万円の人を例にとって試算してみました。
※配偶者や扶養家族がいない状態で、基礎控除のみ差し引いた計算です。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額 |
| 1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
| 1,800,001円~3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
| 3,600,001円~6,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
| 6,600,001円~10,000,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
| 10,000,001円以上 | 2,200,000円(上限) |
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,000円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20 % | 427,500円 |
| 695万円超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
(国税庁 平成29年分~平成30年分 所得控除の算出方法 より:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)
<年収500万円の人の通常の所得税と住民税>
上記の表より年収が500万円の人の所得控除は収入額の20%×+540,000円です。
まずは所得税から計算していきます。
【所得控除】(500万円×20%)+54万円=154万円
【所得税】500万円-154万円-38万円(基礎控除)=308万円(所得控除を引いた所得)
つまり308万円に所得税が加算されることになります。
308万円は上記の表より、税率は10%で控除額は97,000円なので、
308万円×10%-97,500円(控除)=21万500円
所得税は21万500円かかることになります。
次は住民税について見ていきましょう!
住民税の計算方法は下記の通りです。
課税される金額 = 所得金額 - 所得控除 -33万円(基礎控除 すべての納税義務者が対象)になります。
さて計算してみましょう。
【住民税】500万円-154万円-33万円(基礎控除)=313万円
| 課税所得金額 | 住民税の税率 |
| 195万円以下 | ほぼ一律 10% |
| 195万円超 330万円以下 | |
| 330万円超 695万円以下 | |
| 695万円超 900万円以下 | |
| 900万円超 1800万円以下 | |
| 1800万円超 4000万円以下 | |
| 4000万円超 |
(参照:https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1129773.htm)
という住民税率のルールに則って計算すると
313万円×10%+5000円(均等割:所得の大小を問わずすべての納税者に一定金額を課す定額税)-2,500円(調整控除)=31万5千500円
所得税+住民税=53万500円

個人型確定拠出年金に加入していない人だと、どの程度税金がかかるかよくわかったところで、個人型確定拠出年金に加入し、毎月23,000円ずつ積み立ている人についてシュミレーションしてみましょう!
<年収500万円の人が個人型確定拠出年金に加入した場合>
【所得控除】(500万円×20%)+54万円=154万円
【所得税】500万円-154万円-38万円-27万6千円(確定拠出年金12か月分)=280万4千円
280万4千円×10%-97,500円=18万2,900円
【住民税】500万円-154万円-33万円-27万6千円(確定拠出年金12か月分)=285万4千円
住民税285万4千円×10%+5,000円-2,500円=28万7,900円
所得税+住民税=47万800円
個人型確定拠出年金に加入した場合と加入しない場合では、年間53万500円-47万800円=59,700円もの違いがあります。
これは「ただ個人型確定拠出年金に加入し、積み立てただけで増えたお金」だと考えることができます。何もしなくても、約60000万円増えたという計算になります。
節税額を利回り換算すると、なんと21.6%になります。
銀行預金に預けても0.01%という超低金利時代にもかかわらず、ただ個人型確定拠出年金に加入するだけで年間21.6%の金利を得ることができるのです。
これは元本保証のある定期預金に預けた場合の節税効果だけで計算しているので、積極的に投資信託で資産を運用すれば、もっと優秀な利回りを叩きだせる可能性があります。
運用で得た利益は非課税になる
個人型確定拠出年金は元本保証のある定期預金と、元本保証はないが比較的安定性のある資産運用方法「投資信託」を選ぶことができます。
通常、投資信託で得た利益に対して約20%の税金がかかりますが、確定拠出年金で運用した投資信託に関しては税金がかかりません。
普通に投資信託を購入するよりもかなりオトクな仕組みになっています。
受取るときも非課税か控除を受けられる
個人型確定拠出年金を60歳以上で受け取る場合、一時金として一括で受け取るまたは年金として、一時金と年金の併用して受け取るかが選べます。
一括で受け取る場合「一時金受取」といい、「退職所得控除」が適用されます。
受け取る金額と退職金を合わせた金額が退職所得控除より多くなってしまう場合、その分税金がかかってしまいます。
退職所得控除の求め方は以下の通りです。
| 掛金の年数 | 控除額の計算方法 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×拠出年数 |
| 20年以上 | 800万円+70万円×(拠出年数-20) |
(国税庁 参照:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2732.htm)
一時金受取課税額の求め方は以下の通りです。
退職金が多い人は、課税されてしまう可能性があるため、確定拠出年金の受け取りを退職金とずらすことで非課税にすることができます。
一方「年金として受け取る」こともできます。この場合「公的年金等控除」の対象となり、64歳まで年70万円、65歳以降は年120万円まで非課税で受け取ることができます。
運用する金融商品を何度でも変更可能
先ほども少し触れましたが、個人型確定拠出年金で運用する投資信託は何度も売買が可能です(※金融機関によって手数料が異なるので注意)。
例えば、運用している投資信託が右肩下がりで運用成績があまりよくない場合、売却して運用成績のよい投資信託を買い直すこともできます。
ただ、投資信託は長期的な運用で利益を取っていくことが目的の金融商品です。
数日や数か月で「儲からない!」と、次から次に投資信託を変えるのはあまりよくありません。この点は留意しておきましょう♪
本人が死んでも遺族が受け取れる
「そんな長いこと生きるとは限らないし、積み立ての途中で自分が死んだ場合お金はどうなっちゃうの?」と考える人は多いのではないでしょうか。
個人型確定拠出年金は自分の老後のためのお金ですが、積み立てたお金は「ゼロ」にはなりません。

自己破産しても受給資格は残る
仮に自己破産してもなんとか生きていかなければいけません。何が起こるか未知数な未来のためにも、老後のためのお金を確保することはとても大切なことだと言えるでしょう。
厚労省のホームページに確定拠出年金にかかる法律について掲載しています。気になる方は下記のリンクよりご確認ください。
積立すれば無駄遣いが減る
「お金がなかなか貯められない」「ついつい使ってしまう」という人は、確定拠出年金で半強制的に積立をすることは、効果的な貯金の方法だといえます。

個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)のデメリット

3dman_eu / Pixabay
さて個人型確定拠出年金のメリットをお話してきましたが、当然メリットがあればデメリットもあります。デメリットもきちんと確認したうえで加入しましょう。
- お金は60歳まで引き出しできない
- 手数料がかかる
- 運用できる投資信託の本数が少ない
- 途中解約できない
- 投資信託で運用した場合、運用損が出ることもある
- ふるさと納税の寄付額を減らす必要がある
さて、デメリットについて詳しく解説していきたいと思います。
お金は60歳まで引き出しできない
個人型確定拠出年金は、老後の資金をためるのが目的です。そのため当然60歳になるまで引き出すことができません。
通常の預金と違い、「ちょっと途中でお金が必要になったから」といっても途中解約やお金の引き出しは認められません。
ただ次の要件にすべて該当した場合は解約し、脱退一時金として積み立てたお金の返還が認められます。
- 国民年金保険料の納付を免除されていること
- 確定拠出年金の障害給付金を受給していないこと
- 通算拠出期間3年以下、または個人別管理資産(積み立てたお金)が25万円以下であること
- 個人型確定拠出年金の積み立てをやめ、運用指図者※になってから2年以内であること
- 企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
運用指図者とは掛金を拠出せず、残高の運用のみを行う人のこと。(掛金を拠出し、なおかつ運用の指図を行う人は「加入者」といいます。)
この項目すべてに該当することで、中途解約して払い戻しを受ける事が可能です。

しかし解約しなくても掛金の額を減らしたり、積立を一時中断することはできます。収入が減ってしまい掛金を払い続けるのが苦しいというときも柔軟に対処できる制度です。
手数料がかかる
個人型確定拠出年金には月額で手数料がかかることがデメリットです。
手数料は運用する金融機関ごとに大きく違いがありますので、手数料ができるだけ安い金融機関を選ぶことがベストです。
個人型確定拠出年金の月々の手数料負担を少しでも減らしたい場合は、SBI証券か楽天証券で加入するのがおすすめです!
※無料になる口座管理手数料の中に、国民年金基金引落し手数料(一律103円/月額)と信託銀行管理手数料(一律64円/月額)は含まれません。

そうですね!せっかく掛金を拠出し大切に運用しても、高い手数料を引かれてはもったいないです。手数料の安い機関をきちんと確認しましょう!
運用できる投資信託の本数が少ない
個人型確定拠出年金で運用できる投資信託の本数が少なく、いくつもの投資信託に分散投資することが難しくなることがデメリットです。
選択肢が狭められると、いくつもの投資信託に分散投資することが難しくなります。
そこでこのデメリットをカバーするため、個人型確定拠出年金の対象投資信託をできるだけたくさん持っている証券会社を選んで加入しましょう。
SBI証券は個人型確定拠出年金の対象金融商品を約60本持っています。これは他の金融機関と比べても断トツの数です!
SBI証券は口座管理手数料が無料で、たくさんある投資信託から自由な組み合わせで選ぶことができ、投資信託にかかる信託報酬も低く設定されているところが最も大きな魅力であるといえます!
SBI証券のリンクです!是非チェックしてみてください!
投資信託で運用した場合、運用損が出ることもある
確定拠出年金の掛金を定期預金に預けた場合は元本が保証されますが、投資信託で運用した場合は元本保証がありません。
投資信託のメリットとリスクを理解した上で、投資を決める必要があります。
- 定期預金より高い利回りが期待できる
- ドルコスト平均法※で購入価格を平均化することができる
ドルコスト平均法とは投資信託は常に基準価格が変動します。毎月一定額を購入し続けることによって、価格が高いときには少ない株数を、価格が安いときには多くの株数を買い集めることができます。
購入価格を平均化することで価格変動のリスクを取らずに、安定した利益を維持することができます。
投資信託で掛金を毎月積み立てした場合、うまくすればさらに資産を増やすことができるんです。ということは反対に少しの運用損が出る可能性があることもお忘れなく。
Fincleでは投資信託についても詳しく解説しています!是非確認してみてください!
投資信託とは?手数料やリスクはあるの?初心者向けに解説します!
ふるさと納税の寄付額を減らす必要がある
ふるさと納税を利用している人は、個人型確定拠出年金を併用するとき注意すべきことがあります。
個人型確定拠出年金で課税所得が減ると、ふるさと納税で控除される翌年の住民税も減ることです。
「ふるさと納税するときiDeCoで控除される分を計算しなかったせいで、翌年の住民税の控除が思ったより少なく損をした」ということが起こりうります。
このようなことにならないためにも、自分がふるさと納税で寄付しても損をしない上限金額をあらかじめ計算しておきましょう。
個人的には、「月額いくらまで拠出できるか」個人型確定拠出年金をメインに考えることをお勧めします。
それから残り枠でふるさと納税を楽しむスタイルが最もおすすめの方法です。
個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)の加入資格
さて、確定拠出年金の加入資格は以前まで限られていましたが、iDeCoではほぼ全ての人が加入できるようになりました。早速確認してみましょう。
- 企業型確定拠出年金に加入していない人
- 日本国内に居住している人
- 20歳~60歳未満の人
- 国民年金を納付している人
※確定拠出年金は国民年金に上乗せされる年金制度です。そのため国民年金を払っていない人は加入することはできません。また国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている人も、加入することはできません。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者も原則的に加入不可となっています。

企業型確定拠出年金の加入者がその企業を転職・退職した場合、6か月以内にiDeCoに移管手続きを行わなければなりません。
移管手続きをしなければ国民年金基金連合会に「自動移管」され、拠出や運用指図を行えないばかりか、余計に手数料を取られてしまうことにもなります。
そのためきちんとiDeCoに移管しましょう♪
確定拠出年金(iDeCo・イデコ)の掛金の上限金額
確定拠出年金制度は自分で老後の積立をする制度ですが、積立金(掛金)は月額の上限が決まっています!
| 加入対象者 | 掛金上限 |
|---|---|
| 第1号被保険者の加入者 | 68,000円 |
| 第2号被保険者の加入者で企業年金等に加入していない人 | 23,000円 |
| 第2号被保険者の加入者で、個人型確定拠出年金に加入が認められている企業型確定拠出年金に加入している人 | 20,000円 |
| 第2号被保険者の加入者で企業年金に加入している人や公務員、私学共済加入者 | 12,000円 |
| 第3号被保険者の加入者 | 23,000円 |
ちなみに第1号~第3号被保険者、というのは国民年金法で定義されている被保険者の種別で、具体的には下のような人が該当します。
| 第1号被保険者 | 自営業、学生、フリーターなど |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 民間の会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳までの配偶者 |

おわりに

Gellinger / Pixabay
今回は確定拠出年金iDeCoについて見ていきました!制度の内容や加入資格、メリットやデメリットについて理解できましたでしょうか?
最後にもう一度要点を振り返っておきましょう♪
- 『積立』、『運用』、『受取』時に節税が可能
- 運用する金融商品は何度でも変更可能
- 本人が死んでも遺族が受け取れる
- 自己破産しても受給資格は残る
- お金は60歳まで引き出しできない
- 手数料がかかる
- 投資信託で運用した場合、運用損が出ることもある
- ふるさと納税の寄付額を減らす必要がある
- 加入資格を満たさなければならない
かなり簡略化してしまいましたが、これらをおさえていれば問題はないかと思います。
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。